『炭酸泉』と『朝一の白湯』を継続するメリット
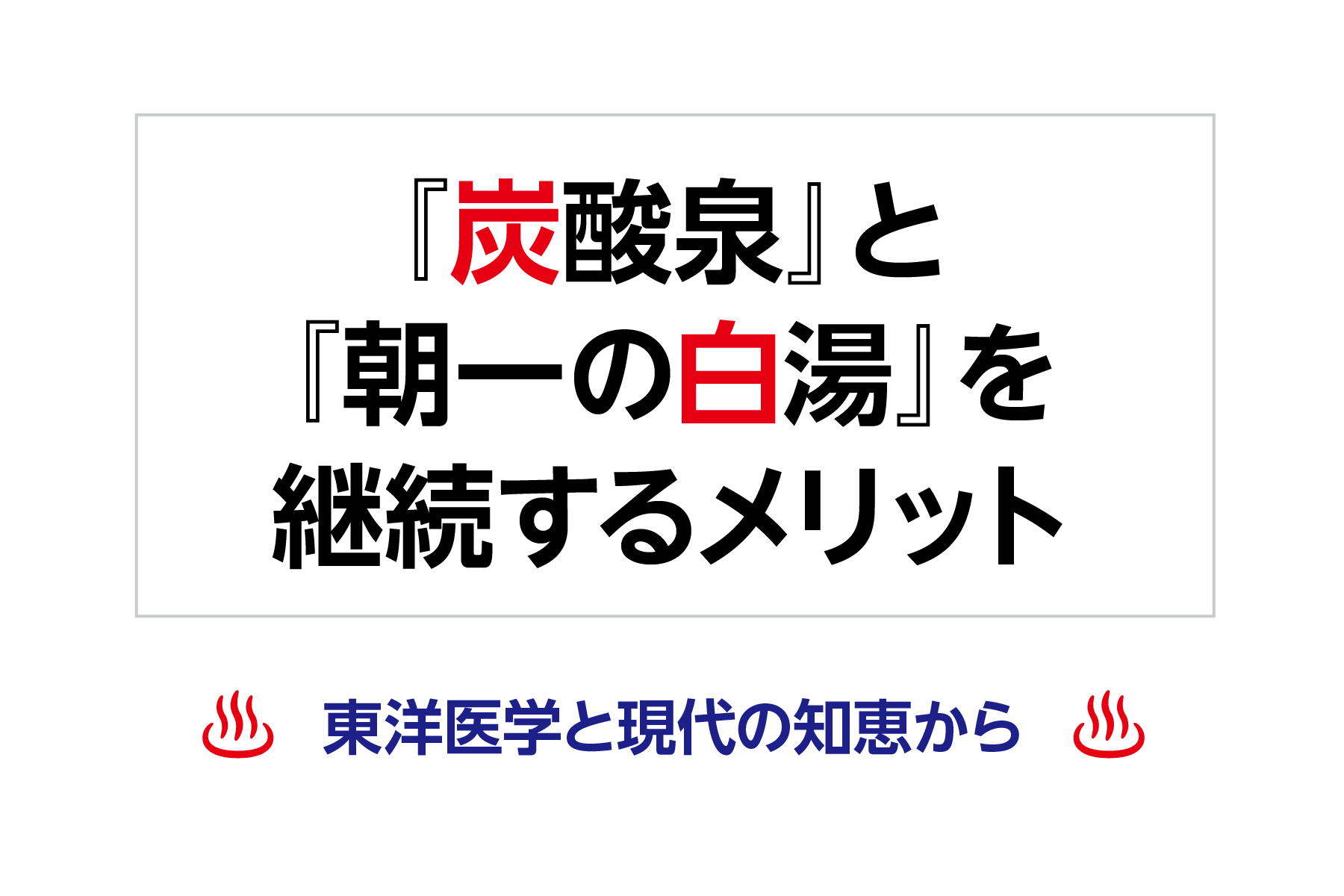
私の習慣から見えてきた健康の知恵
私は現在ライターを続けながら、鍼灸師の資格取得を目指して東洋医学を学んでいる。そんな中で気づいたのは、私が日常的に続けてきた習慣が東洋医学の理にかなっていたということだ。
それは「炭酸泉に浸かること」と「朝一杯の白湯を飲むこと」である。どちらも体をゆっくりと内側から温める効果を持ち、東洋医学でいう「温めて補う(温補)」という養生法に通じる。冷えを防ぎ、胃腸や腎を支え、心身の巡りを整えてくれる。継続することで年齢に関係なく健康の土台を強め、生活の質を高めることができる。
炭酸泉の力 ― 血液からじんわり温める

炭酸泉とは、ぬるめのお湯に二酸化炭素が溶け込んだ浴槽である。一般的な温泉より温度は低めだが、皮膚から二酸化炭素が吸収されると血管が拡張し、血流が促進される。その結果、体の深部体温がじわじわと上がっていく。
熱い湯で表面を刺激するのではなく、血液循環を通じて全身を温めるのが炭酸泉の特徴だ。これにより心臓への負担を減らしながら血流改善が期待でき、冷え性の緩和、疲労回復、血圧の安定などに役立つ。
白湯の力 ― 内臓から体を目覚めさせる

寝起きの体温は一日のうちで最も低い。そんな朝に飲む一杯の白湯は、内臓をじんわりと温めてくれる。冷たい水は胃腸を冷やし働きを妨げるが、白湯は負担をかけず、消化吸収を優しく助ける。
東洋医学では胃腸(脾胃)は「気・血・水」を生み出す工場のような存在とされる。白湯で脾胃を温めれば、栄養とエネルギーがしっかりと作られ、それが腎に届く。腎は老化や冷え、不安感とも関わる臓であるため、白湯を飲む習慣は腎を養うことにつながる。
※東洋医学での 「脾」は、現代医学では「膵臓」を指す。「胃」と「脾」は表裏一体と考えられ、胃が温もれば脾も温もるとされている。
※ 東洋医学では「胃」と「腎」は相克関係とされ、胃が安定していれば腎も安定すると考えられている。
共通点 ― 「温補」という養生法
炭酸泉も白湯も「温めて補う」という養生法を体現している。炭酸泉は外から、白湯は内から、体をゆっくりと温める。この二つを継続すれば、体は気血の巡りを保ちやすくなり、冷えに伴う不調を予防できる。
生活の中で見える具体的な効果
胃腸の不調と白湯
朝に胃が重く食欲がわかないとき、冷たい飲み物は消化をさらに妨げる。白湯をゆっくり飲めば胃腸が温まり、消化吸収が促進される。その結果、便通が整い体も軽く感じられる。
冷えと炭酸泉
手足の冷えに悩む人は、熱いお湯では表面だけが温まり、出た直後に冷えが戻ることが多い。炭酸泉ならぬるめでも血流が促進され、深部体温が長く維持されるため、冷えの改善が期待できる。
腎を養う流れ
夜間の頻尿や慢性的な疲れは腎の弱りと関わることが多い。白湯で胃腸を温めることで栄養が腎に届き、炭酸泉で血流を良くして循環を高めれば、腎の働きが助けられ、活力が生まれる。
精神の安定
ストレスや不安感は心だけでなく腎の弱りとも深くつながる。朝に白湯を飲んで体を落ち着かせ、夜に炭酸泉でリラックスする。この流れが自律神経を整え、眠りの質を高めてくれる。
ぐっすり眠れる毎日へ
私自身、毎日学校で東洋医学や生理学、解剖学を学び、さらに鍼灸の実技に励んでいる。夕方からは仕事もあり、頭はフル回転のままだ。そんな生活だが、ベッドに入れば数秒で眠りにつき、朝はスッキリ目覚める。
思い当たるのは、毎朝の白湯と週末の炭酸泉。この二つの習慣が私にとって大きな支えになっていると感じている。
結論 ― 健康を支える二本柱
炭酸泉と白湯は、シンプルでありながら共通点が深い。どちらも体をゆっくりと温めることで気血の巡りを助け、腎を養い、心身を安定させる。
- 炭酸泉は外から血流を温め、深部体温を上げる
- 白湯は内から胃腸を温め、腎を支える
この二つを継続すれば、体は冷えに負けず、心は落ち着きを取り戻す。特別な道具も薬も必要ない。ただ「炭酸泉に浸かる習慣」と「朝一杯の白湯を飲む習慣」を日常に加えるだけである。
つまり、炭酸泉と白湯は現代人にとって最も手軽で効果的な温養生の二本柱といえる。これを続けることこそ、健康を守り、日々を豊かに生きるための確かな方法である。