ゆみちゃんの銭湯物語
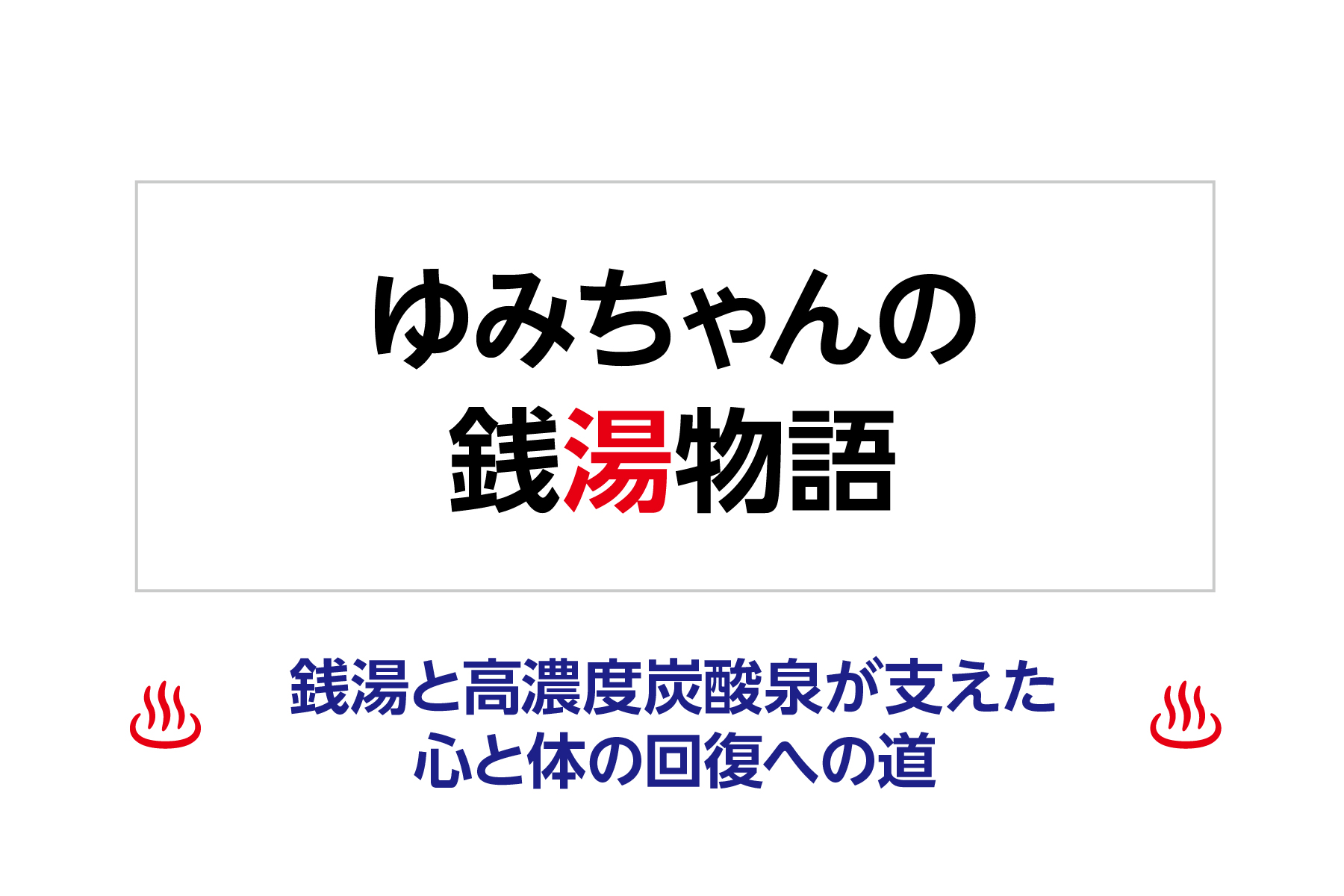
久々の「幸福ゆ」
「幸福ゆ」の暖簾をくぐるのは、何ヶ月ぶりだろう。
松葉杖をつきながら、ゆみちゃんは一歩一歩確かめるように玄関をまたいだ。番台の上でスマホで記事を読んでいた店主が顔を上げ、目を丸くした。
「おやまあ、ゆみちゃん! しばらく顔を見なかったから、心配してたんだよ。」普段は客に詮索をしない店主が、思わず声を上げた。
ゆみちゃんは気恥ずかしそうに笑い、「ちょっとね、大雪の日にやらかしちゃって」と答えた。
転倒と絶望の日々

あの日は忘れもしない。二月の吹雪の夜、仕事帰りに自宅近くの坂道で足を滑らせた。
「ゴキッ」と嫌な音がして、あっという間に雪の上に転がっていた。救急搬送され、診断は複雑骨折。手術と長い入院生活、退院しても松葉杖が手放せない日々。職場に復帰しても、通勤や買い物が億劫だった。
「どうして、私ばっかりこんな目に……。」
40代半ば、独身、母と二人暮らし。父を亡くしてからは家のことも背負ってきた。結婚を約束した人もいたが、それもうまくいかず、気づけば「自分の未来」に期待するのをやめていた。
そんな折に襲った骨折は、まるで「お前はもう何もできない」と言われたように感じられた。心も体も塞ぎ込み、ムシャクシャする日々。休みの日は外出もせず、ただテレビの前で時間を溶かしていた。
「幸福ゆ」の記憶
そんな生活を一年近く続けたある夜、ふと子どもの頃の記憶がよみがえった。
父に手を引かれて通った「幸福ゆ」。90年の歴史を持つ、地元の古い銭湯だ。冬の寒い夜も、湯船に浸かれば心も体もぽかぽかになり、脱衣所で飲むフルーツ牛乳がたまらなかった。
成人してからも、月に数回は通い続けた。自分を取り戻せる場所だったのだ。
「行ってみようかな。」
突然そう思った。身体は不自由なままだが、あの湯に浸かれば少しは気持ちも変わるのではないか。思い立って松葉杖を抱え、タクシーに乗り込んだ。
店主の驚きと温かい勧め
番台から降りてきた店主は、ゆみちゃんの足元を見て息を呑んだ。
「こりゃ大変だったな……。雪でやったのかい?」
頷くと、店主は珍しく親身に耳を傾けてくれた。
普段は必要以上に干渉しない男だが、このときばかりは違った。
「実はな、半年前に高濃度の炭酸泉を入れたんだ。骨や筋肉の回復にも良いって聞くし、血流を促して体の冷えをとってくれる。ゆっくり浸かるといいよ!」
その言葉に背中を押され、ゆみちゃんは浴室に足を踏み入れた。
炭酸泉との出会い
炭酸泉の湯舟は、他の湯より少しぬるめだった。足を入れると、無数の小さな泡が肌にまとわりつき、じんわりと温かさが広がる。
「なんだろう、この感じ……。」
熱さでごまかすのではなく、体の奥にしみ込んでいくような静かな温もりだった。
10分ほど浸かっただけで、こわばっていた足首がふっと軽くなるのを感じた。湯上がりには血の巡りが良くなったのか、松葉杖をつく手まで温かい。
「……これ、続けるといいかもしれない。」
心の奥でそう呟いていた。
週3回のリハビリ銭湯

それから、週に三度「幸福ゆ」に通うことを決めた。母も「いいじゃない、気分転換になるわよ」と背中を押してくれた。
最初は松葉杖が二本。次第に片方だけで済むようになり、数か月後には杖なしで歩ける時間も増えていった。湯舟の中で足首をゆっくり回すリハビリも日課になった。
銭湯の常連客たちも、遠巻きに彼女の回復を見守っていた。
「おっ、今日も来てるな」「顔色良くなったじゃないか」
そんな言葉をかけられるたび、胸の奥がじんわりと温まる。
店主の胸に芽生えた誇り
店主にとっても、ゆみちゃんの姿は励みになった。
炭酸泉を導入して半年、効果をどう伝えるか試行錯誤の日々だった。専門書を読み、他の施設を見学し、コンサルにも相談した。それでも「本当に役立っているのか」と不安は消えなかった。
だが、松葉杖姿で現れたゆみちゃんが、週ごとに回復していく姿を目の当たりにして、胸の奥で確信が芽生えた。
「このお湯は、人を救える。」二本だった杖が一本になり、やがて両手が自由になる。そのたびに、店主の心は躍った。
自分の仕事が人の役に立っている実感。それは商売を超えて、誇りだった。
小走りの日 〜番台前の奇跡〜

ある日の夕方、番台の前でタオルを肩にかけたゆみちゃんが、店主に声をかけた。
「ちょっと見ててもらえます?」
そう言うと、番台前の廊下をすっと小走りしてみせた。足取りはまだぎこちないが、確かに走っていた。
店主は思わず身を乗り出し、「おおっ!」と声を上げた。湯上がりで出てきた常連たちも驚き、自然と拍手がわき起こった。ゆみちゃんは顔を赤らめ、「おかげさまで……」と笑った。
その笑顔は、骨折以来初めて見る晴れやかなものだった。
ゆみちゃんの心の復活
「幸福ゆ」は、ただの銭湯ではない。
父と過ごした思い出の場所であり、今は自分を取り戻すための場所。湯に浸かり、常連の何気ない会話に耳を傾ける時間が、日々の孤独を和らげてくれる。
「ここに来れば、私はまだ大丈夫だ。」
そう思えるからこそ、続けられた。
未来へ走り出す
一年が経ち、ゆみちゃんは日常生活にほとんど支障がなくなった。正座は少し辛いが、通勤も買い物も平気。時には小走りで駅に駆け込むことだってできる。
「人生いろいろあったけど……変わらぬ場所がある。『幸福ゆ』で元気になれたこと、それが今の私の誇り。」
店主も胸を張る。
「炭酸泉を入れて良かった。これからも、ここを“幸福ゆ”の名にふさわしい場所にしていこう。」暖簾は今日も揺れている。
湯気の向こうに、ゆみちゃんの笑顔がある。
銭湯は人を癒やし、人生をもう一度温め直す場所だった。
終わりに
この物語は実在する銭湯で、お客様からお聞きした話をベースに創作しております。物語の骨子は事実に基づいておりますが、登場する人物像や店名はフィクションです。
街中の銭湯に通う人たちは、それぞれの人生を歩みながらも、裸になって同じ湯船を共有する。そこは日本独自の社交場であり、自分を取り戻せる場所でもあるのです。