「身近で、効く」—創業90年の銭湯・たきの湯が高濃度人工炭酸泉を選んだ理由
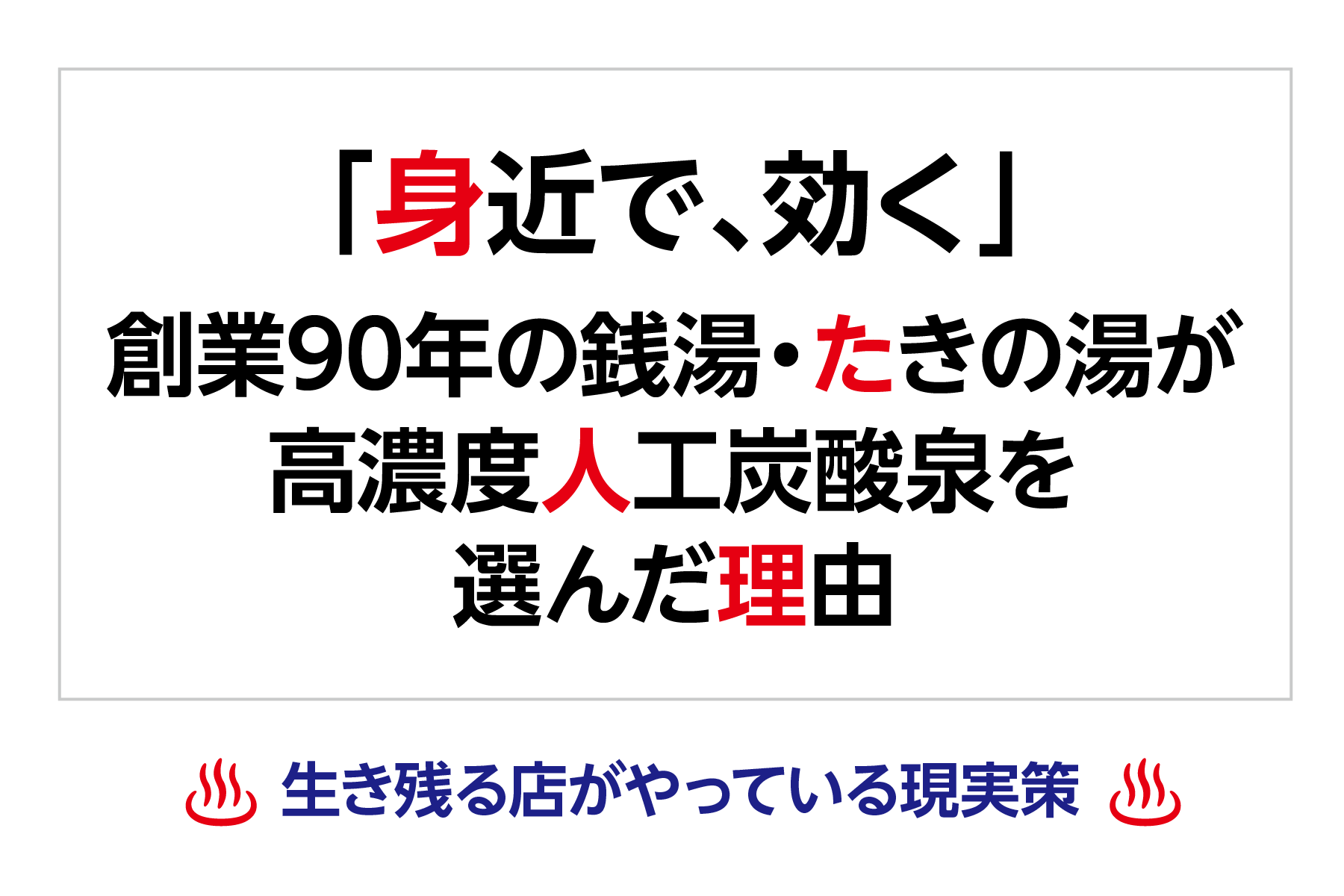
福井県の老舗銭湯「たきの湯」は、2017年の改装で高濃度人工炭酸泉を導入。月間来客は約9,000人から約9,800人へと伸長し、コロナ禍の落ち込みを経て現在も同水準に回復しています。
たきの湯で必要なスペックの装置費は約400万円、付帯工事は装置代と同等〜1.5倍が相場感。投資回収の目安は約2年半──地域密着の銭湯が“次の一手”として炭酸泉を選んだ背景を、オーナーの長谷川多聞さんに聞きました。
施設紹介と時代背景


編集部: まずは「たきの湯」の成り立ちから教えてください。
オーナー: 創業は1935年。福井のまちと一緒に90年やってきました。約30年前に大規模な建て替えを行い、「お風呂のデパート」をコンセプトにサウナ・水風呂・露天・バイブラ・子どもプールまで揃えました。銭湯としては珍しく駐車場も65台確保しています。
編集部: 銭湯を取り巻く環境は厳しいと聞きます。
オーナー: はい。家庭風呂の普及とスーパー銭湯の台頭で、福井県内の銭湯はピークの140軒から今は12軒です。だからこそ“身近で通える健康拠点”としての価値を磨く必要がありました。
導入前の課題は「行く理由」の強化
編集部: 改装前、どんな課題感がありましたか。
オーナー: 銭湯としては近代的ですが、常連さん以外に「初めて来る理由」「また来たくなる決め手」が弱かった。設備は年を追うと陳腐化します。新しい体感を、誰にでもわかる形で用意したかったんです。
高濃度人工炭酸泉という選択
編集部: 数ある打ち手のなかで、なぜ炭酸泉を?
オーナー: “行ったその日に違いがわかる”体感があること。健康イメージが強く、年代を問わず勧めやすいこと。スーパー銭湯より身近な価格帯でも満足度が上がること。この三つが決め手でした。「お風呂のデパート」に、新しい“主役級”を足せると思いました。
実装・費用・回収のリアル


編集部: 導入の実務について教えてください。
オーナー: 2017年の改装に合わせて導入しました。当時の見積もりベースですが、当店で必要なスペックの装置は約400万円くらいだったと思います。浴槽の大きさや、既存の設備によって、付帯工事はだいたい装置費と同程度〜1.5倍が目安。配管や電気容量、ポンプや濾過器などどこまでやるかで幅があります。
編集部: 効果と回収の手応えは?
オーナー: 導入直後に月間来客は平均9,000人→9,800人へ。コロナで一度落ち込みましたが、今は同水準まで戻りました。
炭酸泉の寄与で見れば回収は約2年半の感覚です。実際は建物修繕や他設備の再投悪も同時に行ったのでこの通りではありませんでしたけどね。キャッシュフローは施設の条件次第だと思います。思い切った決断でしたが、“体感の強さ”が口コミと再訪を生み、数字に跳ね返ったのは確かです。
炭酸泉の普及活動
編集部: 炭酸泉を導入した後、効果はすぐに出ましたか?
オーナー: いいえ。正直に言うと最初は苦労しました。改装から半年ほどは業績がほとんど変わらなかったんです。焦りもありましたね。
編集部: その原因はどこにあったのでしょう。
オーナー: 炭酸泉の効果が最も発揮されるのは38〜40度程度のぬるめのお湯なんですが、北陸の方々は熱いお湯にさっと浸かるスタイルが好みなんです。温度を下げると「ぬるい」という声が出てしまい、思い切った設定ができませんでした。
編集部: そこで繁盛している施設を見に行かれたんですよね。
オーナー: はい。実際にいくつかの繁盛している炭酸泉施設を視察してみたら、驚きました。ぬるめのお湯でも湯船はお客さまでぎっしり。みんなじっくり10分以上動かずに浸かっているんです。
ぬるめでも血流が良くなり、体は芯から温まる。深部体温が上がるので湯上がりも長くポカポカしますし、心臓にも負担がかからない。これこそ炭酸泉の力だと実感しました。
編集部: その気づきをどう活かされたのですか。
オーナー: まずは正しい入り方や効能を伝えることにしました。湯船に説明看板を設置し、パンフレットを作って配布しました。時間が許せば、湯船に浸かっているお客さまに直接お話しすることもありました。
編集部: オーナーも一緒に湯船に浸かるのですか?
オーナー: いえいえ、それはしませんでした。それから、公共のスポーツ施設や地元高校にもパンフレットを置かせてもらいました。そして、SNSでの発信も続けましたよ。少しずつお客さまの理解が深まり、炭酸泉の良さが浸透していったと思います。
思わぬ形でのSNS普及効果
編集部: 現在の状況はいかがでしょうか。
オーナー: おかげさまで改装から8年経ちますが、コロナ禍からも完全に回復し、業績は安定しています。特にネット発信の効果は大きいですね。
編集部: 具体的にはどのような成果がありましたか。
オーナー: 「福井 炭酸泉」と検索すると、今では大手チェーンや有名スーパー銭湯よりも上位に表示されるんです。派手なことはしていませんが、コツコツ発信してきた積み重ねが実を結んだと感じています。
編集部: 北陸新幹線の延伸も追い風になっていますね。
オーナー: そうですね。2024年に福井駅と敦賀駅が開業してから、関東からのお客さまが一気に増えました。永平寺や恐竜博物館を訪れた後、検索で当店を見つけて立ち寄られる方が多いです。特に、関西や東海からの車利用客も増えていて、週末には県外ナンバーの車がずらりと並ぶ光景も珍しくなくなりました。
編集部: 地方の銭湯に県外から人が集まるのは珍しいですよね。
オーナー: 本当にそうです。炭酸泉の力と、地道に続けてきたSNS発信。この二つが結びついたことで、想像以上の広がりが生まれています。
オーナーから全国の銭湯経営者へ——「生き残る店がやっている現実策」
編集部: 今年、福井県の温浴(銭湯)組合の理事長に就任されたと伺いました。県内は最盛期140軒から現在は12軒。全国も同様に厳しい状況です。いま、同業の経営者に伝えたいことは?
オーナー: まず前提として、銭湯の多くは個人経営で、置かれた条件も歴史も千差万別。“これ一つの正解”はありません。ただし、共通して言えるのことは—積極的な投資からは逃げられないということです。いつまでも「昭和レトロ」を盾にしていても、お客さまはいつか離れます。“古さ”ではなく“良さ”で選ばれる店に変えていかないといけません。
優先順位①:見えない場所の投資——光熱費を徹底的に下げる
編集部: 最初に手をつけるべき投資は?
オーナー: 損益に直結する熱源の見直しです。多くの施設は重油やガスのボイラーを使っていますが、可能なら薪ボイラーやチップボイラーの導入・併用を検討してほしい。補助金・助成金は遠慮なく活用してください。光熱費が下がれば、すぐにP/Lが改善します。ここは“生き残るための基礎工事”です。
編集部: 炭酸泉のランニングも気になります。
オーナー: この5年で炭酸ガスの仕入れ価格は約1.6倍になりました。だからこそ、導入検討時はメーカー仕様を徹底比較してほしい。CO₂消費効率、濃度の安定性、メンテの容易さ——“燃費の良い設備”を選ぶことが、将来の身軽さに直結します。運用ではムダ噴き防止や濃度設計など、効率の良い使い方を現場で工夫することも欠かせません。
優先順位②:お客さまに“見える”投資——サウナと高濃度人工炭酸泉
編集部: 集客に直結する投資は?
オーナー: サウナと高濃度人工炭酸泉です。
サウナのある施設は、スペースがあれば増設、難しければ内装を清潔・快適に刷新し、温度設定やオートロウリュで湿度に変化をつける。照明・ベンチ・動線を整えるだけでも“サウナファンの刺さり方”が変わります。
加えて、サウナ室の有料化や価格設計で収益化を確保しましょう。入浴料が自治体で定められ自由に設定できない銭湯だからこそ、サウナは重要な収益エンジンになります。
編集部: 炭酸泉は単価アップにどのように繋げますか。
オーナー: 確かに直接の単価上げは難しい。ただ、“街の健康ステーション”としての価値が生まれます。常連の滞在・来店頻度が上がり、健康・美容志向の新規層が増える。実際、私の近所にも長年うちを使ったことがない方がいましたが、「炭酸泉があるなら行ってみよう」と初来店してくれた。入口が広がる設備なんです。
役割を変え、数字を変える
編集部: 最後に、全国の経営者へ一言を。
オーナー: 銭湯の役割は、“家に風呂のない人のため”から、“地域の健康と交流を支える拠点”へと意識的にアップデートすべき時代です。
順番はこうです。
- 熱源の見直しで足腰を強くする(補助金も活用)
- サウナと高濃度人工炭酸泉で体感価値を磨く(見える投資)
- 使い方の啓蒙と価格設計で継続と収益に結びつける
「やるか、やらないか」で差がつく局面です。小さくても、今年ひとつ実行する。それが、次の10年を決めます。
まとめ
データで見る「たきの湯」
- 創業:1935年(90年)/一般公衆浴場
- コンセプト:お風呂のデパート(多様な大型浴槽+駐車場65台)
- 炭酸泉導入:2017年改装時
- 来客(平均):9,000人 → 9,800人(導入直後)→ コロナ期に減少 → 2025年現在ほぼ回復
- コスト感:装置約400万円+付帯工事同等〜1.5倍
- 回収の目安:約2年半
オーナーの一言

「特別な“遠出”じゃなく、日常のなかでちゃんと効く。銭湯はその価値を提供できる場所です。炭酸泉は、その背中を押してくれる強い一手でした。機会があれば導入してください。また、炭酸泉を知らない人に存在を伝える「炭酸泉ラボ」にも期待しています。
(※本記事は取材に基づいて構成しています。数値は当時の実績・感覚値を含みます)
取材先:「たきのゆ」
福井県福井市足羽2丁目17-4
https://www.huroya.com