“熱くも冷たくもない”温度がくれる深い休息
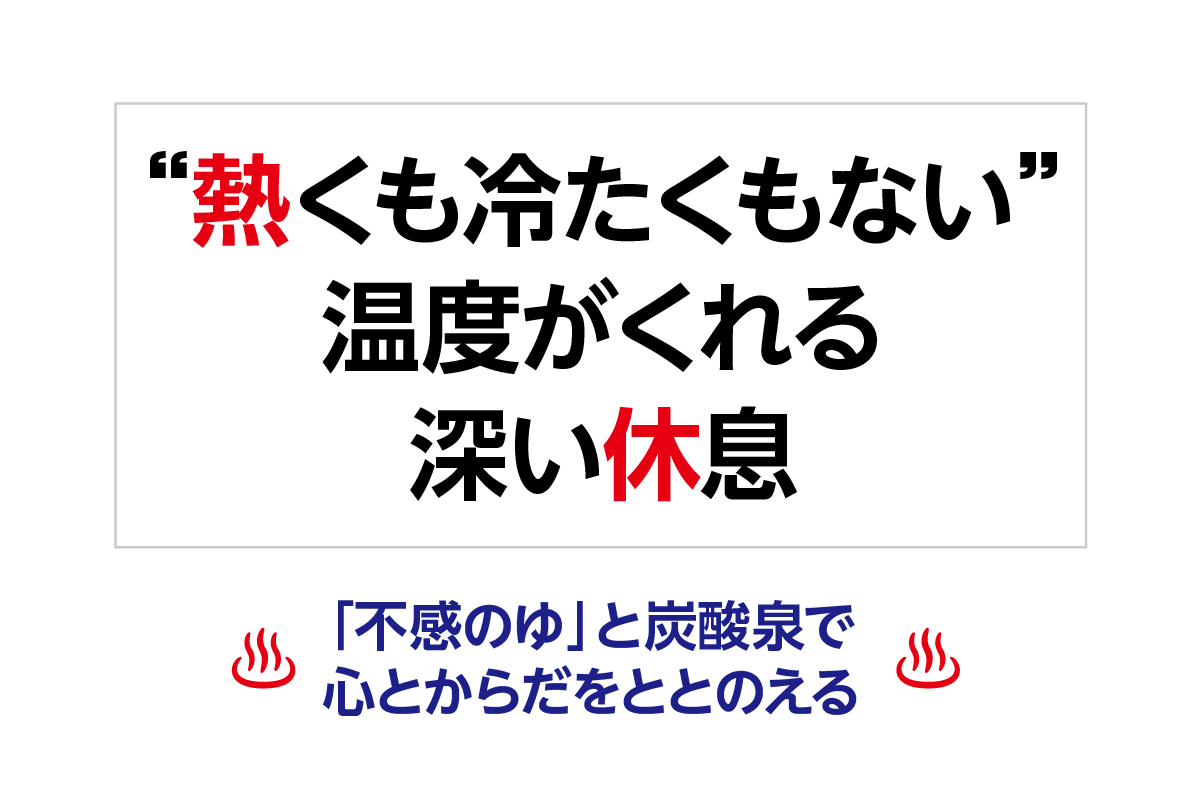
――「不感のゆ」と炭酸泉で、心とからだをととのえる――
暑い日がつづきます。お風呂でさっぱりしたいこの季節、「熱いお湯」や「冷たい水風呂」といった刺激的なお湯ではなく、ぬるめのお湯にじっくり浸かっていたいですね。
「不感のゆ」は、その名の通り、温度を“感じない”自然で穏やかな湯温のおふろ。浸かるだけで、知らず知らずのうちに深い休息をもたらします。今回は、「不感のゆ」の基礎から歴史、具体的な実践法まで整理しながら、忙しい毎日にそっと寄り添う“ととのい”習慣をご提案しましょう。

「不感のゆ」とはどんなお湯?
「不感のゆ」とは、体温より少し低めの33〜35°C前後の湯温で、皮膚の“温度感覚”を刺激しないおふろのことです。
人体の皮膚には温度センサー(温冷受容体)が備わっていますが、32°C付近になるとこれらの感受性が最も鈍くなります。そのため、熱さも冷たさも“感じにくく、交感神経の無駄な興奮が抑えられ、副交感神経が優位になるのです。
銭湯の湯が熱すぎると感じるかたでも、不感温度の浴槽に入ると、「水面と一体化したような浮遊感」が得られ、長時間でも心地よくリラックスして浸かることができます。
温度刺激が極限まで抑えられているため、心拍数の上昇や血圧変動も小さく、誰もが安心して楽しめる“安全な温浴法”なのです。
「不感のゆ」期待できる体の変化
「不感のゆ」は、まさに「整うお風呂」。心身のバランスを回復させる理想的なリラクゼーション空間と言えるでしょう。ぬるめの湯温により副交感神経が優位になり、仕事や家事で張りつめていた緊張が、湯の中でほどけていきます。
熱い湯に比べて発汗が緩やかで、心臓への負荷も小さく、高齢者や循環器系に不安があるかたも安心です。「ストレスを解消したいけれど熱いお風呂は苦手」という現代人にとって、「不感のゆ」は理想的な選択肢となるでしょう。
歴史・文献・フィクションでの“ぬる湯”
不感温度の湯は、江戸時代から現代まで“養生の湯”として日本文化に根付いてきました。
江戸時代の健康書『養生訓』には、「熱湯は血をあおり、冷水は気をそぐ。ぬる湯こそ中庸」と記され、バランスを重視する日本人の健康観がうかがえます。
江戸期の温泉番付には、“微温湯”と称される湯治場が高く評価されていました。これらの湯治場は、慢性的な疾患を抱える人々からも支持されていたのです。
また、ノーベル文学賞作家である川端康成の小説『伊豆の踊子』では、主人公が微温な湯に身を沈め、「心臓が静まる音」を感じる場面が描かれています。文学の中でも、ぬる湯は精神の癒しと結びついて表現されているのです。
このように“ぬるさ”は、治療目的だけでなく、心の静けさを見出す文化的象徴として、長い歴史を持っています。
炭酸泉との親和性
「不感のゆ」と炭酸泉を組み合わせれば、“最強のリラックス浴”が実現します。
炭酸泉は湯温が上がるほど気泡が逃げやすくなりますが、33〜35°Cの不感温度なら炭酸ガスが湯に長く溶け込み、効果を最大限に発揮します。さらに、温度刺激が小さい分、皮膚への負担はごく穏やか。そこに微細な気泡(溶けているCO₂による作用)が血管を拡張させ、身体の内側からじんわりと温まり、ぽかぽか感が持続します。
温めのお湯でも血管が拡張する炭酸泉との親和性は高いと言えるでしょう。
利用シーン・実践ガイド
「不感のゆ」は、専門施設でも家庭でも、ちょっとした工夫で取り入れられます。
温度管理と炭酸発生源という2つのポイントを押さえれば、誰でも簡単に不感炭酸浴を楽しめるからです。
(施設での利用)
炭酸泉装置を備えている施設が前提ですが、装置の温度設定を変えるだけで「不感のゆ」を提供することができます。
医療リハビリ温浴や高齢者向けデイサービスなどでは、「不感のゆ」が積極的に採用されています。浴槽には必ず温度計を設置し、34°C前後の湯温を維持する。長時間の入浴でも疲れにくいと好評です。
入浴施設においては、お風呂の温度は施設運営の重要なポリシーとなります。ゆえに、従来の温度を安易に変えるには運営方針を明確にして、お客様に伝える必要があるでしょう。
運営側としては迷いもあるでしょうが、「不感のゆ」を好むお客様は、思った以上に多いと考えられます。炭酸泉を提供されている施設は、夏場の設定温度を下げて、あえて「「不感のゆ」炭酸泉」をアピールしてみてはどうでしょうか。
(家庭での作り方)
重炭酸タブレット3錠を200Lの湯に溶かし、給湯器のぬるめ設定(約35°C)で湯を張れば、自宅でも手軽に炭酸浴を楽しめます。スマート温度計を併用すれば、湯温の管理も簡単です。
注意点・安全ガイド
「不感のゆ」の恩恵を最大限に受けるには、油断せず安全に配慮することが大切です。
(脱水リスク)
温度が低いと侮らないでください。長湯すれば体内の水分は発汗とともに確実に減少します。入浴前、入浴後の水分補給はしっかりと行いましょう。
(低血圧リスク)
副交感神経の働きで血圧が下がりやすく、立ちくらみや、目眩のリスクが高まります。
連続して浸かり続けるのではなく、時間を区切って浴槽から上がって休む、お湯から出る時は、一回半身浴を挟んで、頭の血を下げる(のぼせ防止)などを意識してください。
まとめ――今日から始める“ととのい”習慣
「不感のゆ」は、忙しさに疲れた心身をやさしく包み込む“体温ブランケット”です。
・ 温度刺激ゼロで副交感神経をオン
・炭酸泉と組み合わせれば温まり持続&血流アップ
・ 歴史が裏付ける安心の入浴文化
まずは週末の夜、34°Cの炭酸タブレット湯に20分。スマホを手放し、ゆっくり呼吸を数えるだけで、深いリラックスと翌朝の爽快感を得られるはずです。「熱い湯=元気」という従来のイメージを超えて、新しい入浴スタイルを日々のルーティンに加えてみませんか。